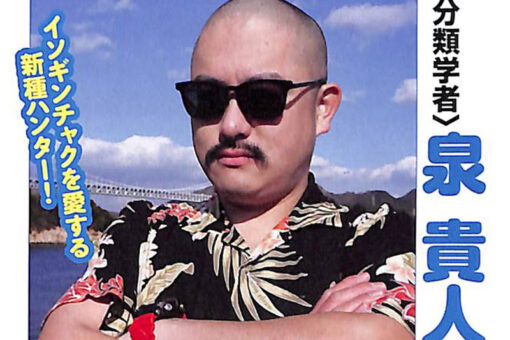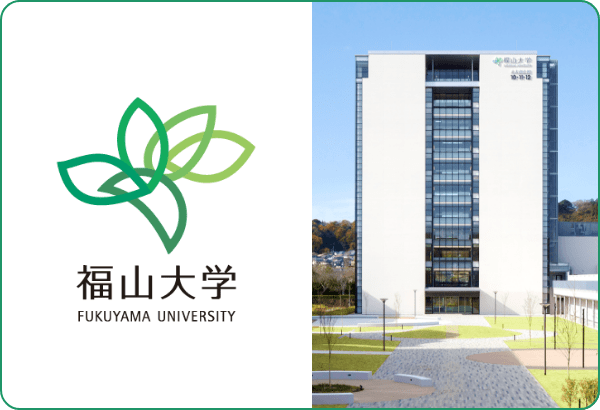【健康栄養科学科】尾道市絵のまち商店会と災害食作り・試食会(訓練)を開催しました!


去る2月15日(土)に尾道市の絵のまち通り商店街の皆様と炊き出し訓練を行いました。同訓練の本学側の実施責任者は、健康栄養科学科の吉田純子准教授です。炊き出し献立の監修、学生指導や商店会様との交渉などを担当し、生命工学部事務室の方々にも支援いただき実施できました。この催しに関する報告が届きましたので、学科のFUKUDAI Mag委員である石井がお伝えします。


この炊き出し練習会(災害食作り)は、絵のまち通り商店街様からお声かけをいただきました。昨今のいくつもの災害を経験し、非常時の食の重要さ・大切さを考えてのことでした。
直ぐに本学科も賛同し、健康栄養科学科学生に参加者を募りました。この日調理した料理は、全て学生考案によるもので食物アレルギーの原因になる食品・成分についても確認して、災害時の食にまつわるリスクの低減も考慮しています。
また、多くの場合調理器具がない、水がない、衛生管理も行き届かないことを想定しているものになります。いわゆる「パック(高密度ポリエチレン袋)でクッキング」となります。

今回初めての炊き出し訓練でしたが、当日は5品(カレーライス、葱入りだし巻き卵、レモン風味キャベツ和え、具沢山中華スープ、レモン蒸しパン)を調理し、尾道市民の皆さんにも振る舞いました。
作り方を1つ紹介します。
「パックdeカレーライス」材料:(ご飯)無洗米と水、(カレー)ツナ缶・玉ねぎ・人参・ピーマン・トマト缶・カレールーと水になります。カレー材料は全てみじん切りにして、袋に全ての材料を入れよく揉み混ぜる。ご飯の袋入りとカレーの袋入りをそれぞれ湯煎で20分程度加熱し、加熱後ご飯は20分、カレーは5分蒸らして出来上がり。
写真は下ごしらえをした食材を袋に入れて、大鍋で煮ている様子です。

実はこんなに沢山のパッククッギングは初めてでした。温度管理や均一に加熱するなど苦労しました。調理上の問題点などもこの訓練で確認できました。

参加学生は1年生から3年生までボランティアで参加の総勢20名(1年5名、2年10名、3年5名)、この他に教員3名(菊田教授、吉田准教授、村上准教授))が、下準備と調理、提供まで楽しく一緒になって行いました。今回提供した料理のレシピや献立構成も学生たちが考えたものです。地産地消も意識して試作を重ねて、調理方法なども最大限災害を想定したものにしました。
厚生労働省が「災害時食の指針」を示しており、それに基づく栄養基準を基に作成し、勿論、管理栄養士として衛生管理にも配慮し、食中毒や感染症のリスク低減も勘案したものになっています。

絵のまち通り商店街の皆様や実施関係者の方々、本学科関係者とNHKの取材スタッフもこのイベントを取材・身守って下さり、とても賑やかな会となりました。実際の災害時では、こうはいかないかと思いますが、何よりも平時の訓練がいざという時に効果を発揮しますよね。

訓練会を通じて反省点もいくつか見つかり、さらに改善していこうと話し合い、盛会のうちに終了しました。寒くはありましたが、屋外での訓練会で、お天気に恵まれ良かったです。



吉田純子准教授 連絡先:e-mail j_yoshida@fukuyama-u.ac.jp 電話:084-936-2112(内線4042)
学長から一言:健康栄養科学科の教員と学生の皆さんが、近隣の尾道市「絵のまち通り商店街」の皆様からの呼びかけに応え、協力して「炊き出し練習会」を開催。いつ、どこで起こるか分からない災害に備え、日頃からの心構えと訓練こそ大切とばかり、本格的な災害食づくりで、日頃の学びの成果を地元の皆様にもご披露できたのは素晴らしい!