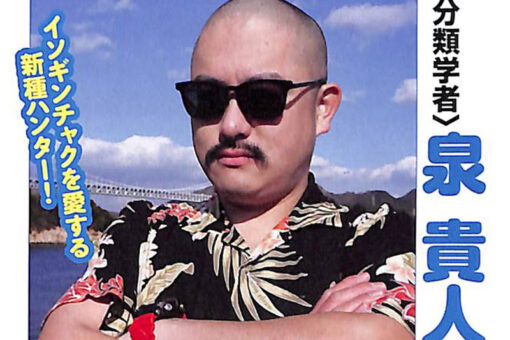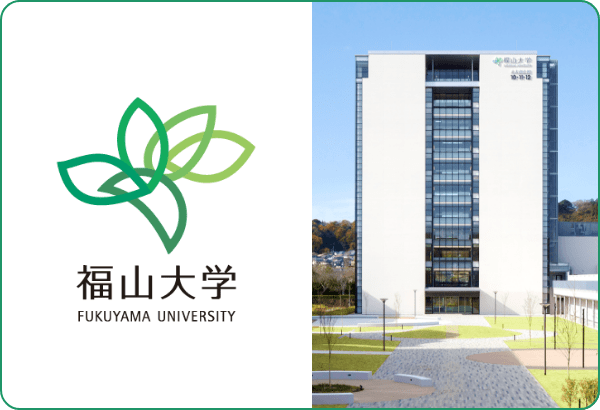【サークル】学友会海洋生物研究会〜尾道市のアマモ花枝採取活動に参加しました!〜

海洋生物研究会広報担当の奥井です! 5月24日に、尾道市と浦島漁協が協力して実施されている「アマモの花枝採取活動」に参加しましたので報告いたします。(投稿は、海洋生物科学科FUKUDAI Mag委員の阪本)
尾道の海のゆりかご(干潟・藻場)再生による里海づくり
現在、尾道市ではブルーカーボン・オフセット推進事業『尾道の海のゆりかご(干潟・藻場)再生による里海づくり』という活動が実施されています。そのカギとなるのが“アマモ場”の再生事業です。私たち部員の多くが所属する海洋生物科学科では、すでに所属教員が研究者として活動に参加していますが、自分たちも実際に現場に出て現状を知り、私たちにできることを探るべく、今回の活動に参加させていただきました。野外での調査活動には部員からも多くの手が上がりましたが、今回は初めてのことでもあり、10名を選抜しての参加となりました。
始めに尾道市農林水産課の古屋野様から、採取するアマモの花枝についてご説明いただきました。

事前説明
「花枝」とは、春になると伸びてくるアマモの生殖株です。葉の上につぶつぶした花をつけ、いずれそれは種になります。今回はこの花枝を採取して桟橋に吊るし、発芽させるための種の熟成作業を行いました。たくさんのアマモの中から、このつぶつぶがついた生殖株を見つけます👀

アマモの花枝
ここで、つぎの写真の中から一緒に花枝を探してみましょう🔍

見つかる?
ヒントは右下です! もう少し近づいてみましょう・・・

見つかる?
少しだけ明るい色のアマモをよ~く観察してみると…

見つかる?
ありました!! このように目を凝らしてどんどん「花枝」を見つけていきます。

収獲!
開始20分でこの量!!すごい👏

収獲!!
こちらはとても長い「花枝」を発見したようです!
アマモ場は「海のゆりかご」とも言われるように、多くの生き物の生育・産卵場所となっており、餌場や隠れ家など様々な活用がされています。採取中にも色々な生き物を発見しました。

ミミイカ🦑

テッポウエビ🦐

ハゼの仲間

ツメタガイの卵のう

タマシキゴカイの卵

コウイカの卵

産卵中の巻貝

たくさん採れました
1時間ほどで採取は終了。前の2人が特に多くの花枝を見つけました!! 最後は先ほどのネットの中のアマモと一緒に重りとなる石を入れ、桟橋に吊るします。

浦島漁業協同組合の松若隆博組合長(手前)と当研究会の今村部長(奥)

桟橋熟成
ここで秋まで熟成させます。
活動の成果
今回の活動に参加した学生からは、次のような感想があがりました。
・実際にアマモ場に入って、そこの生き物と触れ合うことで生態系を知ることができた。アマモへの関心がさらに深まった。
・学ぶことが多く、貴重な経験をすることができた。
・花枝採取中に多くの生物や卵を見つけ、アマモ場が「海のゆりかご」と呼ばれる理由を実感できた。
この活動を通して、アマモ場の機能などを実際に観察し、肌で感じて、学びを深めることができました。現場の作業では人手不足や高齢化が深刻な問題となっていることも知り、若い力として我々が参加することで、課題の解決につながることも理解できました。何より、私達も干潟の現状や改善について知ることができる本当にいい機会となりました。今後も干潟でのアサリ資源の保護に向けた取り組みへのお手伝いなど、尾道市や浦島漁協との連携を深め、様々な活動に挑戦していきたいと思います!
学長から一言:尾道沿岸の海の環境を守り、漁業資源を守るために重要な意味を持つアマモ場を再生させる活動に参加した海洋生物研究会の皆さん、お疲れ様でした。地元の方々と一緒になって汗を流し、「海のゆりかご」づくりに協力できたのは素晴らしい! 皆さんの努力が報われ、豊かな海が戻ってくることを祈ります。