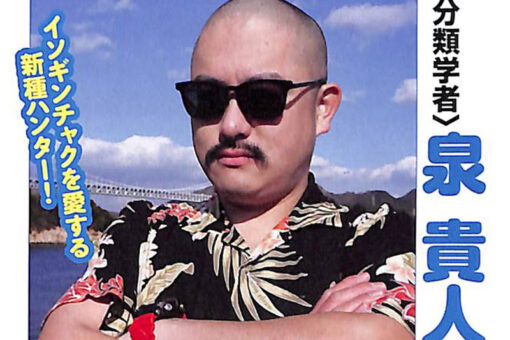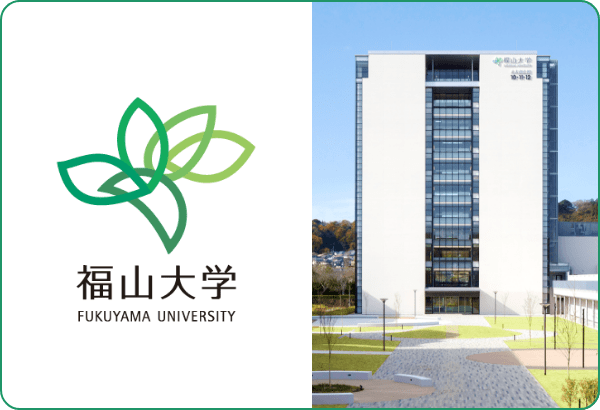【建築学科】国宝の寺 浄土寺の見学に行きました!(日本建築史)

みなさん、こんにちは!
建築学科では、2年生が学修する「日本建築史」(担当:佐藤圭一教授)という科目があります。以前に、明王院の見学に訪れた様子をこちらでご紹介しました。今回は、国宝である尾道の浄土寺の見学に訪れた様子をFUKUDAI Magの学科委員であり、引率補助した大畑から紹介させていただきます。
浄土寺は、福山市のお隣、尾道市にあります。浄土寺は国宝である本堂や多宝塔、国指定重要文化財である阿弥陀堂など多くの文化財の宝庫であり、現在では「身代り観音さまの寺」、「茶の寺」、「文化財の寺」として親しまれています。尾道水道を背に参道を上がると「山門」(国指定重要文化財)が見えます。

山門から参道を振り返ると、線路が参道の上を走っているのがわかります。

山門をくぐると、国宝である「本堂」が正面に見えます。本堂の建物が国宝であるだけでなく、この境内の土地も含めて国宝として指定されています。
写真には写っておりませんが、たくさんの鳩が棲み着いており、白い鳩の絵馬も飾られていました。

本堂の中ではまず浄土寺の小林さんにご説明いただき、それから本堂をはじめ浄土寺の建物を徳岡伝統建築研究所の徳岡秋雄さんに解説いただきました。前回訪れた明王院の解説もしていただいた徳岡さんは宮大工であり、かつ一級建築士資格をもつという職人さんです。
建具が外されており、外陣(学生が座っている側)から奥にある内陣を直接見ることができました。特別に内陣、脇陣にも入らせていただきました。内陣の仏様の上を見上げると「二重折上小組格天井」という、教科書で習った日本建築最高格式の天井意匠がありました。

続いては、本堂から阿弥陀堂へ移動しました。内陣の随所に施された装飾は一つ一つ手仕事でつくられたものであり、どれほど貴重な場所であるかがわかります。特に卍崩しの装飾を施した蟻壁は、ここでしか見られない逸品です。

阿弥陀堂から方丈(これも国指定重要文化財!)へ移動し、見学は続きます。方丈にも見どころがたくさんあり、美しい襖絵、築山や枯山水のある庭園が印象的です。また、畳縁(たたみべり:畳のへりに付けられている布)が段によって違い、奥の畳縁には柄が施され(紋縁)、手前の畳縁は無地でした。昔、畳縁は色や柄の違いによって格式を表していた名残のようです。


最後に見学させていただいたのは、国宝「多宝塔」です。赤い扉の上に「蟇股(かえるまた)」があり、牡丹の花や蝶の透かし彫りがされています。(その名のとおりカエルの脚のような赤い枠の中に彫刻されています。)

こちらも特別に内部を見せていただきました。塔の中を見せていただける機会はめったにありません。学生も緊張しながら、中へ入っていきました。
多宝塔の中にも繊細につくられた装飾があります。徳岡さんから部分ごとの名前やその特徴などを丁寧にご説明いただきました。特に彩られた絵様肘木は、他では見ることのできない貴重なものです。学生は熱心にメモを取りながら聞いていました。

2回にわたり、「日本建築史」の見学会の様子をお伝えしました。教科書等の写真だけでは感じ取ることのできない様子や、普段公開されていない場所を見ることができる大変貴重な機会でした。身近にこれだけの寺院建築内部を体験できることも稀ですが、それを建築の学習のために一部特別に見せていただきました。浄土寺の小林さん、徳岡さん、ありがとうございました。
聞くところによると、他の科目でも実際の建築や街並みを見に行く授業があるとのことです!またこちらでご紹介したいと考えています。
※本記事で使用した写真はいずれも掲載許諾をいただいております。この場をお借りして感謝申し上げます。
学長から一言:建築学科の授業「日本建築史」の一環で訪れた尾道の浄土寺には国宝等に指定された建物が多くあり、本学の近場にありながら、寺社建築の伝統様式を学ぶには恰好の場所のようです。未だ訪ねたことのない私も、今回の特別拝観の場所も含めて、この記事に書かれた丁寧な説明と写真でその素晴らしさを感じ取ることができますが、やはり百聞は一見にしかず、実際に見てみたいものです。