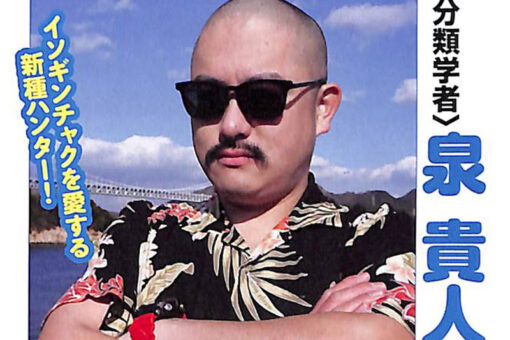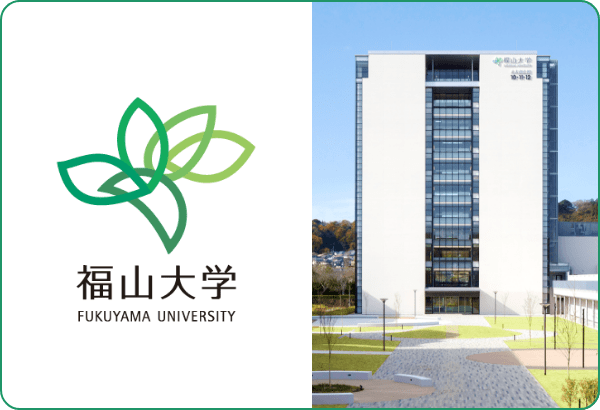【人間文化学科】三菱財団人文科学研究助成による 「「福山義倉」の文化的ネットワークとその継承―菅茶山と井伏鱒二を軸に―」 研究報告書完成

三菱財団人文科学研究助成による「「福山義倉」の文化的ネットワークとその継承―菅茶山と井伏鱒二を軸に―」(2023年~2024年、研究代表者・人間文化学部教授青木美保、同清水洋子准教授、柳川真由美教授、福山平成大学教授市瀬信子教授、兵庫教育大学名誉教授前田貞昭氏)の研究報告書が完成しました。
本研究は、備後圏域経済・文化研究センター文化部門のプロジェクト課題研究を母体とする研究であり、本学のブランド研究「瀬戸内の里山・里海学」の一端です。2024年度は、本学予算による文化フォーラム4回とシンポジウムを連動させて本研究の総括を行いました。
以下は、青木教授を中心に11月30日に開催されたシンポジウムについての報告です。(投稿はFUKUDAI Magメンバーの古内)。

実施報告 備後圏域経済・文化研究センター文化部門主催シンポジウム
「「福山義倉」の文化的ネットワークとその継承―菅茶山と井伏鱒二を軸に―」
―福山義倉創設220年に当たって―
本研究は、対象とする年代が1750年代後半から1930年代初頭まで180余年にわたり、また、空間的には大坂、備前・備中・備後、讃岐、筑前と西日本全域にわたるものですが、今回のシンポジウムによって、西国街道神辺宿の文化的ネットワークに焦点化して、「福山義倉」の成立背景を描き出す第一歩を提示することができました。
※シンポジウム当日の状況 来場者 42名
アンケートには、基調講演について、江戸後期の経世思想家「中井竹山」について初めて知ったこと、政治家には、人格の完成―知性だけでない「品性」―の必要性を感じたこと、研究発表の内容については、江戸後期の地域のリーダーから学んだことが現代の政治に生かされればよいという感想、また井伏鱒二の江戸期の記憶が家庭の中の女性による語りに支えられていること、江戸の一揆の際に菅茶山の姿勢に思いをはせたことといったことが書かれており、今後の研究成果の継承の必要性を感じさせました。
まず、関連講演会も含めたシリーズの講演会の全容を以下に示します。
▲大学予算による講演会・文化フォーラム4回、地域資料活用研修1回の計5回の講演会
文化フォーラム
第1回 9月21日(土) 中井竹山と「社倉私議」
講師 清水光明氏(東京大学グローバル地域研究機構特任研究員)
第2回 10月12日(土) 「諸国無類」の義倉運営―「福府義倉」の独自性について―
講師 平下義記氏(広島経済大学経済学部准教授)
第3回 10月19日(土) 菅茶山の福祉思想と朱子学
講師 清水洋子(福山大学人間文化学部准教授)
第4回 11月16日(土) 備後圏域における『孔子家語』の読まれ方
講師 市瀬信子氏(福山平成大学経営学部教授)
地域資料活用研修 地域の偉人シリーズ3
10月26日(土) 江戸後期福山大庄屋の知恵に学ぶ地域運営―信岡家の古文書から見えること
講師 山名洋通氏(ひろしま文化功労者、元新市歴史博物館館長)
▲三菱財団人文科学研究助成によるシンポジウムと関連展示
11月30日(土) 「福山義倉」の文化的ネットワークとその継承―菅茶山と井伏鱒二を軸に―
開会挨拶 大塚豊 本学学長
基調講演 「中井竹山の経世論」 湯浅邦弘氏(大阪大学名誉教授)
問題提起 江戸後期備後圏域における地域運営と文化的ネットワーク 青木美保(研究代表者)
研究報告
1 「菅茶山の福祉思想」 清水洋子(本学准教授)
2 「近世の朱子学受容」 市瀬信子氏(福山平成大学教授)
3 「近世庶民による「孝行」の絵画化と継承」 柳川真由美(本学教授)
4 「近世近代移行期の文化人の文学的ネットワーク」 前田貞昭氏(兵庫教育大学名誉教授)
まとめ 青木美保
▲展示「福山義倉」と儒教教育―「備前邑久岩佐家旧蔵書」(門田朴斎旧蔵書を含む)から
11月29日・30日 福山大学社会連携推進センター802研修室
「福府義倉」の活動(『義倉二百年史』、文化フォーラム資料から)、「儒教教育」資料「孔子家語」「孝経大義」の版本展示(福山大学寄託資料「備前邑久岩佐家旧蔵書」、福山大学附属図書館、福山平成大学附属図書館所蔵資料から)
※以下に、シンポジウム(11月30日13:00~16:30、福山大学社会連携推進センター)の報告をします。
開会の挨拶
大塚豊学長から、備後圏域経済・文化研究センターが地域の文系研究の拠点として2020年に開設されたこと、本研究が、本学理系研究者によってはじめられた福山大学ブランド研究「瀬戸内の里山・里海学」の文系研究分野の研究であることが示され、本学における地域研究の全円的な体制が整ったことが宣言されました。
基調講演 湯浅邦弘氏「中井竹山の経世論」

1 講師紹介
湯浅邦弘氏は、大阪大学懐徳堂センターのセンター長(2009年~2023年)を長年務められた懐徳堂研究の第一人者です。先生のご講演は、中井竹山の学問、および社会的活動の特徴を分かりやすく解説するもので、本研究で取り上げた茶山の場合とのつながりがおのずと見えて来るものでした。
※懐徳堂について
(懐徳堂は、1724(享保9)年に大坂の豪商が出資して設立した学問所で、将軍徳川吉宗によって官許学問所となったが、運営は設立の商人たちによってなされた。中井竹山は、懐徳堂最盛期の塾頭。懐徳堂は1869(明治2)年に廃止、1916(大正5)年再建、戦後は大阪大学文学部が継承している。なお、茶山の廉塾は、1791(寛政3)年創設。)
2 講演概要
1,懐徳堂の教育理念―「修己治人」と「経世済民」
まず、懐徳堂の教育理念は、懐徳堂の入り口に掛けられた看板(「入徳門聯」と呼ばれる)に記された「修己治人」と「経世済民」という二句、すなわち自己修養と社会貢献にあることが説明されました。また、塾内の規則「定書」の第一には、塾生同士が「貴賤貧富」の別なく「同輩」であること、つまり自由平等を第一としていることが語られました。
2,「経世済民」活動
そして、竹山の活動の要点は、学問を世の中の民を救うものとすること、「経世済民」にあるとされました。現代でも使われる「経済」の原義はそこにあるとの現代社会への問題提起もありました。
さらに、その竹山の経世思想の具体的展開に、竹山の活動の特色を示されました。第一に経済面で、食物の流通に関して、朱子社倉法に想を得たシステムとして、国家管理の「常平倉」、民間主導の「社倉」による物価安定策、「義倉」による備荒貯蓄策などの政策、インフラ整備については大井川架橋への提言、教育については、学校の衰えは社会の衰えであるという理念の下、教育改革についての提言、その他社会運営における多方面での提言があり、それが時の為政者・松平定信への献策につながり、寛政の改革が実現したことが説明されました。
3,中井竹山の活動の特色
最後に、それらの活動が、習俗因習を打破する合理主義、人・物・金が集積する大阪という都市を背景とした広い視野と情報収集、朱子学の「修己治人」の理念を中核とする高い見識と実学的傾向が相まって実現したとの結論を示されました。
※この中井竹山の学問的姿勢が、菅茶山を接点として江戸後期の福山藩内にどのように伝わり、廉塾創設、「福府義倉」創設につながったのか、それが本研究の主題です。
問題提起 研究代表者・青木美保「江戸後期備後圏域における地域運営と文化的ネットワーク」

※講師 日本近現代文学専攻、宮沢賢治研究、井伏鱒二研究で著書あり。
「福府義倉」創設220年の記念の年に当り、本研究を、「福山義倉」関係者の皆さんに捧げることを宣言しました。
1 本研究対象の人物関係年表について
年表には、菅茶山・井伏鱒二を中心とする関係人物30人の生没年を記し、その生没年を一人一人矢印で縦に結びました。年表の縦を辿ると、一番古い古川古松軒の生年(1726・享保11年)から一番新しい井伏鱒二の没年(1993・平成5年)まで、約270年弱の期間が、断続的な矢印によって重なりながらつながります。これを全体でみると、福府義倉を立ち上げ、実施し、幕末まで維持していくのに、およそ3世代の層が関係していることが見えて来るのです。その実態を、最初に概観してもらいました。
2 井伏鱒二と江戸時代の記憶―祖母の語る百姓一揆の話し
年表で概観したことを、年表の最も新しい人物・井伏鱒二の自伝的作品「半生記」における幼少期の記憶にたどりました。井伏の幼いころには、村にまだ江戸時代生まれの人がおり、その人達から昔の話を聞くことが出来たとあり、その中で祖母の昔語りに出て来る百姓一揆のことが特筆されています。それは、天明の一揆のことらしく、百姓の申し入れが聞き入れられた全国でも珍しい事例であり、井伏が、そこに「知恵者」の存在、一揆のリーダーとしての「庄屋」に注目していることを指摘しました。
井伏の社会観がこれら庄屋の社会観に基盤を持つのではないか、そして、それが、井伏が昭和初期に左傾化しなかった要因の一つにあるのではないかという問題提起を行いました。
3 「福府義倉」成立の時代背景―江戸時代後期の社会転換期と西国の儒学者の学問転換
これまでの近世後期の歴史家の研究成果を踏まえて、1800(寛政12)年が江戸時代後期(1750年~)の社会転換の年に当たり、その前後40年間(1780年~1820年)を江戸時代後期の社会転換期とするという説を紹介し、廉塾創設(1791年)、福府義倉創設(1804年)が、いずれも新しい社会への福山藩内の対応であったことを示しました。その期間においては、田沼意次時代の商業奨励による貨幣経済の発展で窮乏生活に追い込まれた農民、武士の暮らし方が変動し、そのことは、特に天明の飢饉(1780年代後半)を契機として天明のうちこわしなど、社会の上下関係に危機的状態を引き起こしました。
その社会的危機に当たって、学問においても、旧時代の学問・古文辞学派(原典に帰って言葉の意味を規定していく方法をとる学派)への批判が巻き起こり、朱子学本来の現実対応的な学問に立ち返る学派が台頭しました。古文辞学派が江戸から広がったのに対して、朱子学正学派は、京都・大坂から始まり、西国の儒学者たちが主導しました。そこに中井竹山も位置し、菅茶山も、西山拙斎、頼春水も同時期に古文辞学から転向しました。
4 福府義倉の特徴―藩民共営・共栄の互助システム
福府義倉は、中井竹山の「社倉私議」を参考にしていると、発起人の河相周兵衛が述べています(後述)。「社倉私議」は、米の備蓄とその運用方法についてのシステムですが、彼が仕えている龍野藩に建言したものの、採用されませんでした。清水光明氏の講演によれば、それは、豪農と藩とが出し合って元米を積み立て、その管理は学者が当たり、受益者は民間限定というものです。
これに対して、「福府義倉」の特徴は上下両方にとって有益なシステムであるところにあり、平下義記氏の講演によれば、資金は豪農商層と藩が負担し、管理は豪農商層が行い、受益者は藩民両方、ということで、その八方受益の柔軟な運用方法に特徴があると言えます。その運用理念の特徴は、「貯めこまず」使うことで「国用」に立てることで物も金も「宝」になるという考え方にあります。その使途の廉塾への資金援助、民間への教育費、奨学金、寺社の普請費などは他藩にないものとのことです。
※「福府義倉」は、設立者らによって「諸国無類の義倉」とされています。そのような独自性のあるシステムはどのように成立したのか、その成立背景、あるいは現代まで続いた背景にはどのような地域の文化状況があるのか、その他の研究報告へと移りました。
研究報告1 「菅茶山の福祉思想」 清水洋子

※講師 中国文学、中国思想専攻、夢占の研究で、著書あり。菅茶山の福祉思想。
1 近世江戸における「福祉思想」
「福祉」の概念の歴史的変遷を踏まえて、菅茶山の対社会の思想および活動を明らかにするものです。近世江戸における「福祉思想」は儒教における個人倫理「仁愛」と公的な「仁政」が不可分の関係にあるという説をとり、その展開として近世近代移行期のあり方として、貝原益軒、二宮尊徳の「仁愛」思想など儒教倫理の人民への普及に寄与した、自己修養的な実践活動を取り上げています。
2 茶山の福祉的思考と地域社会へのまなざし
これに対して、菅茶山の「茶山先生行状」、「冬のこかげ」、政治についての意見書、「誠意説」を資料として、茶山の「福祉思想」を明らかにしています。それは、次の3つにまとめられます。
●儒教の伝統的な「仁政」に沿った民衆撫育を願うが、それが行われない現実に直面し、恒産と礼楽の必要性を指摘、救恤については「経世的思考」を明確に持っていること。
●民衆という存在に対して、「恒の心なく」「何も不存」と現実的に認識し、奢侈を懸念、「たのしミ」に通じる家庭道徳のひろがりを広めていくこと。
●「誠意」(『大学』第六章)に個人的修養としての本質を見ているのではないか。
特に、「誠意説」においては、「慎独」を肝要としながら、朱子の「慎独」解釈に疑義を示し、自身の解釈について述べていることを指摘しており、茶山の学問を深めていく独自の研究姿勢が見えてきます。
研究報告2 「近世の朱子学受容」 市瀬信子氏

※ 中国近世文学専攻 乾隆帝時代の文学者の研究。
寄託資料「備前邑久岩佐家旧蔵書」(門田朴斎旧蔵書を含む)における『孔子家語』の書入注を取り上げて、そこに備後地方において、儒学がどのように展開したかを考察するものです。
1 「孔子家語」とは
『孔子家語』は、『論語』に含まれない孔子の言動を収録した書物で、魏の王粛が弟子の家に伝えられたものを入手して世に出したとされます。しかし、王肅が偽作したものという説が宋以後に優勢となり、更に清代考証学の中で偽作説が検証されるに及び、偽作説が決定化していったという受容の経緯が説明されました。
2 江戸時代の『孔子家語』受容
中国の否定的評価に対して、日本では、徳川家康が「聖賢の奥義」を伝える書として『孔子家語』を公刊したことから、広く読まれ、高く評価されてきたと思われます。寛政異学の禁の際に教育制度が整備され、「昌平坂学問所」が設置されると、そこに中国の各種の「孔子家語」の注釈本が所蔵され、更に全国の藩校・私塾にいたるまで、「孔子家語」が整備されました。
3 江戸時代における『孔子家語』注釈書
日本で広く読まれたのは、日本人の優れた注釈書の力によるところが大きいとのことです。
岡白駒『補註孔子家語』、太宰純『補注孔子家語』、千葉玄之『標箋孔子家語』、塚田虎『冡註孔子家語』、高田彪『孔子家語合註諺解』などの諸本が紹介されました。これらは、古義学(古文辞学)派、折衷学派の学者が取り組んだものが多いが、学派を越えて長く読み継がれることとなりました。
4 備後圏域における朱子学と古義学
福山藩では、二代藩主阿部正福以来、古義学派が継承されましたが、寛政異学の禁により朱子学派に転じとされます。ただ、菅茶山関係資料には、古義学派の書物も確認され、頑なに古義学を否定したとはいえないと判断されます。
5 備後圏域における『孔子家語』注釈本
1,廉塾蔵書『標箋孔子家語』10巻5冊
広島県立歴史博物館所蔵の菅茶山関係資料には、太宰純増註、千葉玄之の『標箋孔子家語』が確認され、書入注も見られることから、廉塾でも古文辞派の注釈による『孔子家語』が読まれていた可能性があります。
2,寄託資料「備前邑久岩佐家旧蔵書」における「孔子家語」
「備前邑久岩佐家旧蔵書」は、広島大学名誉教授・竹村信治氏から研究代表者・青木に寄託されたもので、門田朴斎旧蔵書を含むほか、廉塾や誠之館の蔵書㊞を持つものを含む354点を指します、この中に、太宰純『増註孔子家語』がありますが、その一巻には多くの書入註があり、それは、当時の福山藩内での「孔子家語」の読解の現場を知る貴重な資料との解説がありました。
この書入注を、他の流布本と比較検討した結果、書入注は考証学的検証によるものであること、ただしその書入れに基本的なミスがあることから、書入注の基となったものがあり、それを写した人物が知識人ではないことが推察されます。また、内容的には太宰春台の執筆部分に注釈を加えていることから、日本の学者によるものであると考えられます。内容的には批判的読書の姿勢が見えるとともに、これが講師による講義の内容をメモしたようなものである可能性を示されました。
そこから、本資料が当時の学ぶ人たちの学びの実態を垣間見ることのできる貴重な資料であるとの判断が示されました。
研究報告3 「近世庶民による「孝行」の絵画化と継承」 柳川真由美

※講師 近世文化史・服飾史専攻、近世豪農の文化活動とネットワーク、神辺本陣資料の調査・研究
1 備前の大森家の例
大森家には、初代当主満體(通称武介)の複数の肖像画が存在し、それが、すべて宝暦6(1756)年10月3日、満體47歳のときのもので、善行のために藩主から「御褒美のお米3俵」を下賜されたことを子孫に伝えるためのものであったことが、種々の資料によって明らかにされました。そのことは、「備前孝子伝」に「篤実で仁愛深い武介」が、「日ごろから貧しい人たちを助けていた」ことを奨励する旨記載されていることから見えました。特に宝暦6年の飢饉の際に、社倉の麦だけでは支援がいきわたらないとき、自らの蔵を開いて人々を支えたことが書かれていました。
2 大森満體肖像画作成における文化的ネットワーク
大森(大國)家には、満體の名前も載っている『官刻孝義録』50冊がセットで所蔵されており、それは、遺された書状から、この本が笠岡在住の親戚北村六郎治を介して、面識のない茂平村の庄屋増二に購入してきてもらったことが判明しているとのことです。
また、満體の肖像画の一枚の賛について、遺された書状からそれが、大森文助が、交流のある有吉蔵器を介して、岡山藩校の教授・近藤篤に依頼して書いてもらったものであることが判明しているとのことです。このように、身近な人を介して文化的事跡にアプローチして文化財を取得し、文化的地位を上昇していく当時の人々の行動様式がうかがえます。
研究報告4 「近世近代移行期の文化人の文学的ネットワーク」 前田貞昭氏
 ※講師 日本近代文学専攻、井伏鱒二研究で著書あり。
※講師 日本近代文学専攻、井伏鱒二研究で著書あり。
井伏鱒二の父・井伏郁太=素老、そして、井伏の福山中学の同級生高田類三の父・高田品治=桃蹊は、いずれも興譲館に学び、漢詩をよくする文学愛好者でした。
本研究は、かれらの文学活動の実態を、彼等が参加した詩社回天詩閣発行の漢詩専門誌『詩』の運営状況から考察し、近世近代移行期の備後圏域在住文学者の動向について明らかにするものです。
『詩』は、洋紙に活版印刷で、各号30頁ほど、明治27年1月から29年1月にかけて、深津郡福山町の先進堂から全21冊が刊行されました。編集・運営の主体となった回天詩閣閣員(妹尾秋江、浜野穆軒、後藤蘆洲)、『詩』の寄稿家組織であった回天詩閣協賛員(発足時は井伏素老=郁太・高田品次=桃蹊ら7人)は、いずれも備後・備中で実績を持つ20歳代の若手漢詩人たちでした。この『詩』においては、備後・備中に住む年長の漢詩人たちが課題詩の選者、啓蒙的記事の書き手、そして、主要な漢詩寄稿者として協力しています。また、『詩』を機に著名漢詩人の歓迎会、観梅の会などの詩会が催されています。『詩』が若手漢詩人の発意で突然出現したのではなく、地方漢詩専門誌を支えるに十分な備後・備中漢詩壇の活動と人の繋がりがあったと考えられます。
『詩』については、①備後・備中の20歳代の若手漢詩人たちが、フラットな関係を前提に、②年長の漢詩人をも巻き込むことに成功して、③備後・備中漢詩壇に隆盛をもたらした漢詩専門月刊誌とまとめることができます。
井伏郁太は、明治26年末、『詩』創刊と時期を合わせるかのように、備中西江原の生家を離れて、養家先の備後粟根井伏家に移ります。それと同時に興譲館を辞めます。そのことについて、素老は、「与佐伯禅麿書」(『日本詩文雑誌』第3巻第63号、明治27年5月1日、2頁~3頁)では「隠鴨里故捷〔「故捷」は「故棲」とあるべきでしょうか〕」と書き、「隠居」「隠在」などと言っています。
しかし、今日の私たちが使う「隠居」などという言葉とは違って、素老が、世間から身を引いて、一切の交わりを絶ったわけではありません。粟根に「隠居」した素老は、『詩』を主な発表舞台として、一挙に活発な創作活動を展開します。素老の粟根転居と重なるように創刊された『詩』という新たな舞台が、素老に活躍の場を提供したと言ってよいでしょう。素老は、回天詩閣に「協賛員」として関わり、『詩』に漢詩を発表するのはもちろんのことですが、詩会(詩を作る会合)に出席したり、漢詩人のもとを訪問したりして、備後・備中漢詩壇に一定の地位を占めるに至ります。
単純な延べ数では、素老は、明治25年は16首、明治26年は21首の漢詩を発表していたのですが、明治27年は53首、明治28年も45首に跳ね上がります。素老の生涯で最も活発に漢詩を発表していた時期です。その内、『詩』には明治27年と明治28年とを併せた88首の半数程の55首を発表しています。
他方、素老は、興譲館同窓会機関誌『同窓誌』第3号(明治28年1月)と第4号(明治28年6月)の、一切の事務と編輯兼発行者を引き受けます。
中央漢詩壇との関係を切断したわけでもありません。明治25年に始まる『日本詩文雑誌』への投稿も毎月のように継続し、森川竹磎が興した鴎夢吟社の機関誌『鴎夢新誌』にも素老の名前が出ます。
素老は、粟根に退きはしても、新たなネットワークの中に身を置き、また、興譲館や中央漢詩壇との関係も続けます。つまり、東京(江戸)に遊学して漢詩人として名を成すのとは異なる、地方漢詩人(在地漢詩人)としてのスタイルを模索していた……と考えられます。
ところが、素老の漢詩発表数は激減します。『詩』終刊の明治29年になると素老は9首(『詩』は明治29年は1月に1冊しか出ていません)、明治30年と明治31年にはそれぞれ3首の漢詩しか発表していません。その一方で素老は広島県農会に入会し、農会の機関誌や農業関係誌に素老の寄稿が見られるようになります。
漢詩実作を目的とした『詩』に、直接に義倉に関する言説は見られません。しかし、義倉を支えたのに通じるような、経世済民の観念の持ち主が回天詩閣の関係者にいなかったわけではないことも指摘しておきましょう。回天詩閣協賛員や寄稿家たちの多くは、その後、実業・社会事業・政治の分野で活躍し、漢詩文の教養を文化資産として有する地元名士の道を歩みますが、社会貢献を心掛けた人々もいます。高田桃蹊は村会議員・村長の任に就き、仏教系の博錬教黌再建運営に注力しましたし、同じく協賛員であった妹尾芳外=吟一郎も銀行頭取・酒造会社取締役・村会議員・興譲館理事を勤め、俳句結社を主宰し、さらには自宅に柔道場を開いて後進の指導に当たったことを付け加えておきたいと思います。
総括 「福府義倉」成立の文化的ネットワーク 青木美保
※講師 日本近現代文学専攻、宮沢賢治、井伏鱒二で著書あり。
1 「義倉発端手続」に見る事の興りと文化的ネットワーク
「義倉発端手続」は、「福府義倉」の発起人・河相周兵衛が死の二年前に書き遺した記録で、その成立の一部始終を知ることができます。そこにあったのは、西国街道の神辺宿における人的交流であるということができます。そこには、縁戚のつながり、庄屋同士のつながり、文人化した庄屋の他藩士とのつながりがあります。それは、地域を超え、身分を越えて一つの目的に向かう情熱です。
石井武衛門(深津村庄屋)が、娘婿に「遺金」を「御国用」に役立ててほしいと遺言した。
河相周兵衛(千田村庄屋)と信岡平六(戸手村庄屋)が神辺で宿泊時に、その使途について相談した。
藤井暮庵が備中岡田藩(下道郡岡田村、現倉敷市真備町)の藩士に尋ね、その家老から中井竹山「社倉私議」を借り た。藤井暮庵(河相周兵衛の三歳年上)は、神辺の庄屋の息子、菅茶山の最初の弟子。
筑前秋月藩(現福岡県朝倉市)の藩士、亀井南冥の諸生が家老に話し、亀井その人に意見を聞くことが出来た。(神辺本陣は、福岡藩の参勤交代の際の定宿)
以上のように、「福府義倉」の成立には、庄屋たちの公共の利益への強い思いがあったのです。それは、菅茶山の蒔いた学種の開花と言えないでしょうか。
2 文化人のサロンの継承
菅茶山の周囲には、住む場所を越え、学派を越え、身分を越えて様々な人々が文学を通して交流するサロンがあり、それが社会運営にもつながったと考えられます。そこには、学問・倫理を踏まえた経済活動がありました。
そして、そのサロンの存在は、明治期の井伏郁太・高田品治の文学活動につながり、それは、大正期の井伏鱒二・高田類三の福山中学時代の絵画サークルに、また昭和期の第二次世界大戦直後の府中市の文化サロンにまでたどることができます。
以上のように、ここには、学問に裏付けられた倫理と経済活動の融合、その活動を支える文化サロン的人間関係の絆を見ることができます。
それは、江戸後期の福山藩内で生まれた「福府義倉」の周辺にあったものです。今後は、その生活の厚みを現代に伝える活動を続けていきます。

学長から一言:三菱財団人文科学研究助成を受け、2年がかりで実施された研究「“福山義倉”の文化的ネットワークとその継承―菅茶山と井伏鱒二を軸に―」の締め括りとして昨年11月実施されたシンポジウム。本学のブランド研究「瀬戸内の里山・里海学」の一環でもある同研究は、青木美保教授のリーダーシップの下で推進され、実に多彩な内容を包含しています。この報告を読むと、改めてシンポジウム当日の様子が蘇ってきます。