学部・学科・大学院
心理学科
山崎 理央(やまさき りお)
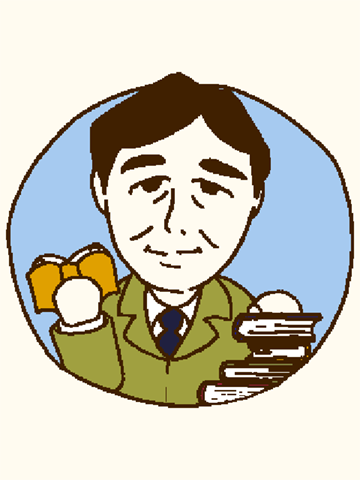
| 職 名 | 教授 |
|---|---|
| 学 位 | 修士(心理学) |
| 専門分野 | 臨床心理学 |
| 担当科目 | パーソナリティと適応、臨床心理学、臨床心理学課題実習、臨床心理学専門ゼミなど |
| メッセージ | 私の専門である心理療法は、心についての理論をバックボーンとした、心の悩みや問題を抱える人への援助という側面を持ちます(現在の臨床実践としては、主に精神科クリニックでカウンセリングを担当しています)。 臨床心理学は「臨床」という名が示すように、心の多様性にライブにかかわる魅力があります。 |
カウンセリングの理論や技法
心理的な対人援助において「傾聴」の姿勢は重要です。相手に寄り添い関わるうえで、まずは相手の語りをじっくりと聴き受け止めることが援助の第一歩となるからです。しかしこの「傾聴」自体、対人援助の際に望ましい形態を表す言葉であるとして多用されるものの、その意味合いは抽象的であり、言葉のイメージが一人歩きしている印象もあります。実際の援助場面で援助者自身が味わう迷い・とまどいといった感情はどのような意味を持ってくるのでしょうか。

セルフヘルプ・グループの機能と特徴
セルフヘルプ・グループは、生きるうえで何らかの同じ問題やテーマを抱える本人や家族などの集まりです。このセルフヘルプ・グループは現在いろいろな形で存在し、自主的に生まれ専門家から独立した運動を展開している、当事者による持続的な小集団という点に特徴があります。当事者だけでなく、当事者に関わる専門職の人々による関心が高まってきており、そこでは従来の「援助者-被援助者」という関係とは異なる新たな視点や問題点が投げかけられています。






