
【経済学科】2024年度卒業論文:学部長賞受賞コメント
経済学部では2022年度(後期卒業)より、論文完成度、作成努力度、教員指導度といった観点から評価付けを行い、特に優秀と経済学部長が認めた卒業論文に対し「経済学部長賞」を授与することとしています。2024年度の経済学科の受賞者4名と受賞コメントを紹介します(昨年度の受賞者とコメントはこちら)。
①池田琉星さん(総合経済コース 高羅ゼミ 山口県・桜ケ丘高校出身)『ベストプラクティス企業の事例研究―男性の育児休暇を当たり前に―』
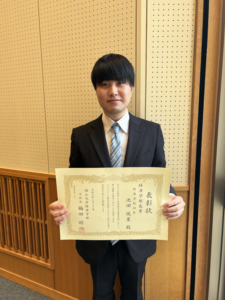
テーマを選んだ理由
就職活動をするなかで、結婚・子育てなど自分の将来についても考えるようになりました。そんな中、3年ゼミ生の発表を聞く機会があり、広島県の男性育休取得率が実は全国と比べて高いことを知り、よい機会なのでその理由や企業の取り組みについて調べてみようと思ったからです。
苦労したこと
14社に6項目の調査を行い、どの企業からも詳細な回答をいただいたため、質問ごとにまとめなおし、共通点を見つけ分析し、改善に向けた提案を行う作業が大変でした。
工夫したこと
図表は着目したいところだけ色づけし、男女で色を分け、イメージがわきやすいように画像も載せました。取り組みについては、第1章の現状と照らし合わせて、3項目にわけ、ホームページ等をもとに自分で分類しました。卒業論文では共通点と提案は文章だけになってしまいましたが、プレゼンでは箇条書きにし、色付けをし、要点が一目で伝わるように工夫しました。
成長したこと
自分の中で今日はこれだけやろう、今週中にここまで終わらせようといったゴールを設定し毎日コツコツ取組まないと、結局最後に泣くことになるので、計画性が身についたと思います。
学んだこと
仲間の大切さです。執筆するのは自分ですが、一人で考えていても行き詰ってしまうことも多く、ゼミ等での議論や助言は有益でした。下宿先でゼミの仲間と執筆をがんばったのもよい思い出です。
後輩へのアドバイス
当初は別のテーマで進めていましたが、いざ調べてみると、思うようなデータがなかったり、すでに議論されていたりと行き詰ってしまいました。漠然とテーマを考えるのではなく、早くから情報収集をし、ほんとにそのテーマで進めていけるのか見極める必要があると痛感しました。どこにテーマのヒントがあるかわからないので、常にアンテナを張り巡らせて、普段の講義やゼミでの他の人のプレゼン、ニュースも自分事として考え、いろいろなことに興味をもつことが大切だと思います。
②小林慎弥さん(スポーツマネジメントコース 野田ゼミ 広島県・盈進高校出身)『サッカーのゴールキーパーに求められる能力と評価に関する研究』
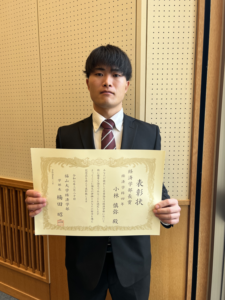
テーマを選んだ理由
一般的にはゴールキーパーはシュートストップが高く評価されますが、ゴールキーパーとして活動してきた自身の経験から、他にも評価できる能力(例えば、試合中に唯一フィールド全体を見渡せるポジションなので、状況を的確に把握し味方に指示を出す能力など)があると思ったため、このテーマを選びました。
苦労したこと
文字数が13,000字と多いこと、どういう順番で説明したら読み手に伝わるかという構成を考えることに苦労しました。
工夫したこと
多くのデータを集めるために、私の所属する福山大学サッカー部の部員だけでなく、他大学の部員などにもアンケートの協力をお願いしたことです。
成長したこと
どういう質問をしたら研究目的に合ったデータを収集できるか考え、分析する前には収集したデータの処理をする必要があるなど、自分が思っていたより時間と労力がかかりました。この経験から計画的に進めていくことの大切さに気付くことができた点が成長したことだと思います。
学んだこと
データが多いほど分析での信頼性の向上に繋がることを学びました。
後輩へのアドバイス
私は大学でもサッカーをしており、卒業後も続ける予定で、興味を持っていたゴールキーパーの評価をテーマに卒業論文を執筆しました。日ごろの練習で、どうすれば監督から評価されるか、どうすればよいゴールキーパーになれるかなどを考えることはありますが、データを分析して考えることはなかったので、執筆を通して新たに気づくこともありました。自分の好きなことや経験してきたこと、興味があることをテーマにした方が楽しみながら取り組めるので、書きやすいと思います。
③高橋詩音さん(総合経済コース 田中ゼミ 広島県・如水館高校出身)『総合型地域スポーツクラブがスポーツ実施率に及ぼす影響』
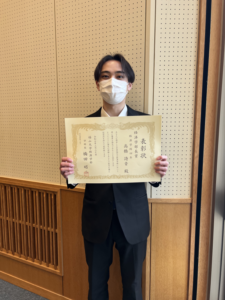
テーマを選んだ理由
小学生のころからバスケットボールをしており、スポーツ分野に興味があり、近年学校部活動の地域移行が問題になっていることから、中高生が部活動に参加できる環境づくりに興味をもったからです。
苦労したこと
総合型地域スポーツクラブという組織を軸として研究しましたが、比較的新しい取り組みのため、参考となる先行研究が少なく、なかなか思うように進まなかったことです。
工夫したこと
図やグラフなどのレイアウトやフォントを工夫しました(例えば、1ページにおさまりかつ文字などが見づらくならない大きさにしたり、伝えたい事柄を大きくするなど)。
成長したこと
「計量経済学」で学んだ回帰分析を用いて論文を執筆することができたことが一番の成長だと感じています。
学んだこと
自分が立てた仮説と結果が異なっていても失敗ではなく、そこから新しいことを発見できたり、疑問が出て新たな研究につながるものだと学びました。
後輩へのアドバイス
論文は一朝一夕で完成するものではありません。あまり興味がないものを題材にしてもだらけてしまうので、気になることや興味があることをテーマに執筆するのが一番だと思います。
④近森一樹さん(総合経済コース 楠田ゼミ 広島県立日彰館高校出身)『排出ガス規制で生産終了したバイクの価格形成要因の研究』

テーマを選んだ理由
バイクが好きで中古車サイトを閲覧したり販売店に行った際、環境規制以前に生産されたバイクの方が規制に対応しているバイクより価格が高いという現象に疑問を感じたからです。
苦労したこと
中古車情報を公開しているサイトやサンプルデータが限られていたこともあり、データ集めに苦労しました。
工夫したこと
独自の分析だけでなく、先行研究との比較分析を行い、結論の相違点や共通点をより明確に説明したことです。
成長したこと
論文を執筆するなかでどのデータが必要なのか、読み手を納得させるにはどの資料や図表を使えばよいかなどを自分で考え、時には先生や友達に相談し、論文完成に向けて地道に取り組んだことです。
学んだこと
自分の意見だけではなく、客観的なデータや分析、資料を交えることの大切さを学びました。
後輩へのアドバイス
実際に取り組み始めると、データや文献の収集などに予想以上に時間がかかってしまうこともあるため、早めから取り組むことが大切だと思います。そのためにも自分の興味や関心のあるテーマのほうが書きやすいと思います。





