
【情報工学科】教育におけるコンピュータに関する国際会議で学部生と教員が発表!
広島市内の国際会議場にて、教育におけるコンピュータに関する国際会議WCCE2022が開催され、本学からは工学部情報工学科4年生の三宅君と山之上教授が発表を行いました。このことについて、情報工学科の山之上と中道が紹介します。
**********************************************************
8月20日(土)から8月24日(水)までの5日間、広島市内の国際会議場でZoomなどを使ったオンライン会場と結んで、教育におけるコンピュータに関する国際会議 WCCE2022(World Conference on Computers in Education, https://wcce2022.org)が開催されました。この会議は、Towards a Collaborative Society through Creative Learning(創造的な学習による協調的な社会を目指して)をテーマにして開催され、本学からは工学部情報工学科4年生の三宅君(広島県立神辺高等学校出身)と私(山之上)が発表を行いました。

WCCE2022のホームページ
WCCE2022は、1960年にユネスコの提案により設立された国際機関IFIP(International Federation for Information Processing, 情報処理国際連合, http://ifip.org )と日本の情報処理学会(https://www.ipsj.or.jp)が共同で開催したものです。この他、デジタル庁、文部科学省、総務省、経済産業省、広島県、広島市等の団体の後援を受けています。WCCEは、1970年から開催されていたのですが、今回はアジアで初めての開催だったそうです。
基調講演には、ジャズピアニストで数学研究者の中島さちこ氏(https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/459001.html)、台湾政府のデジタル担当政務委員として有名なオードリー・タン大臣、教育用プログラム開発環境として有名な BlueJやGreenfootの開発者でもあるKing’s College LondonのMichael Kolling教授、学習解析(Learning Analytics, LA)の第一人者である緒方広明教授といった錚々たる方々が招かれて、とても興味深い講演を聞くことができました。

オードリー・タン氏の基調講演
また、文部科学省大臣官房審議官の安彦広斉氏、経済産業省教育産業室長の浅野大介氏、広島県の平川理恵教育長、昭和女子大学キャリアカレッジの熊平美香学院長、慶応義塾大学の鈴木寛教授、IFIP TC3委員長で英国Lancaster University大学の Don Passey教授による、日本のICTとSociety 5.0の教育政策に関するパネルディスカッションも開かれました。
この他、世界中から集まった85本のフルペーパー(長い論文)、39本のショートペーパー(短い論文)、27件のポスター等による発表が行われました。
三宅君の発表は「Comparison of Teaching Environment in Hybrid-Flexible Class」という題で、対面授業やテレビ会議システムを用いた同期型オンライン授業、LMS等を用いた非同期型授業について、受講者のアンケート調査を実施した結果に基づいて報告したものです。

三宅君の発表

三宅君の発表時の会場の様子
私(山之上)の発表は「Five Years of Experience in Improvement of a Technical English Class Using Information Technologies」という題で、以前に学長室ブログで紹介したことがある専門英語の授業(<情報工学科>授業「専門英語」の紹介, http://blog.fuext.fukuyama-u.ac.jp/2017/01/blog-post_17.html)を5年間に渡って改善したことについて述べたものです。この改善には、福山大学全体で行われている授業評価アンケートの結果も利用しています。新型コロナウイルスの感染拡大で、対面授業で利用していたRaspberry Piという小型コンピュータが、オンライン授業では利用できなかったことについても述べたのですが、その理由は何か?についての質問がありました。また、エストニアから来ていた座長からは「5年間の成果をまとめたことは素晴らしい。おめでとう。」と言ってもらいました。
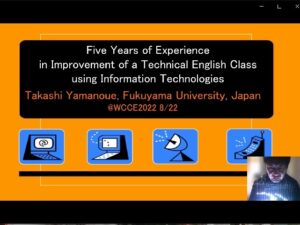
山之上教授の発表の様子
学長から一言:教育におけるコンピュータに関する世界的な会議で専門家である山之上教授の発表が行われたのも誇らしいことですが、日頃からその指導を受けている4年生の三宅君が別のテーマの研究発表を単独で行ったのはなお素晴らしい! 教員が身を以て手本を示し、学生はその姿を見ながら成長する、情報工学科の「師弟同行」の教育が着実に実を結んでいることの表れです。





